について
- 専門基礎養成

「図書館」の世界に閉じることなく、社会や地域、文化や経済との関係のなかで未来の図書館を一緒にはじめませんか。「図書館」を主語にするのではなく、私たち一人ひとりを主語にしてみませんか。「知識はわれらを豊かにする」(長尾真)ために「図書館」をどう再設計(リ・デザイン)できるのでしょうか。このプロセスで注目しているのが、産官学民の連携(「クワトロヘリックス」)による「共創」です。本講座自体、この考え方に基づきデザインされています。ぜひ、共に知り、共に創るプロセスにご参加ください。第2期ではカリキュラムの流れを組み換えたほか、新たに「子育て支援」「図書館DX」という特別なトピックに注目した講座も追加しています。また、第1期生のみなさんの経験と提案に基づき、対話型のオンラインゼミの実施等を予定しています。また第1期ではコロナの影響で実現できなかった、argのプロジェクトへのインターン参加も実現していく予定です。
次世代図書館専門課程の概要
| 内容 | eラーニング + オンラインゼミ + 集中研修(※コロナ禍の状況が収束している場合、集中研修は視察も兼ね現地開催に切り替える場合もございます。) 【eラーニング】 16週間程度のレクチャー動画、課題図書の読破、動画および図書に対するレポートの提出 【オンラインゼミ】 ZOOM等のオンライン会議ツールを利用したゼミナールの実施。日程につきましては、参加者のみなさんのご都合を考慮して決定します。 【集中研修】 開講式研修(半日)、修了式研修(2日間)の計2回 【任意研修】 arg社のプロジェクトの実践にインターンとして参加していただける機会を提供します(現地参加の場合、旅費は各自負担となります/各自で現勤務先との調整や機密保持の誓約が必要となります)。 |
|---|---|
| 主催 | アカデミック・リソース・ガイド株式会社(arg) 及び プロフェッショナルスクール株式会社 の共催、(協力)⼀般社団法⼈公⺠連携事業機構 |
| 定員 | 40名(最小開講人数 15名) |
| 受講料 | 55万円(受講料50万円+消費税5万円) 受講料に関して、条件を満たす場合に特典割引がございます。 詳しくは、「申込特典について」をご参照ください。 |
| 資格・条件 | 社会人経験者を対象とします。事前選考を実施します。 ・政策目標として図書館政策に力を入れたいと考えている公務員 ・図書館整備の実践に取り組もうとしている方(公務員、図書館関連団体・企業、設計者など) ・図書館への新しい経営手法の導入について学びたい方(公務員、図書館関連団体・企業、設計者、研究者など) ・情報通信技術の進展により拡張する図書館の創造にチャレンジしたい方(公務員、図書館関連団体・企業、設計者、研究者など) |
- 最小開講人数 15名
紹介動画
開講スケジュール
- 2021年度(第2期)
| 申込・選考 | 現在、「仮応募」受付中となります。ご受講をご希望の方は、まずは仮応募をお願い致します。 【仮応募受付期間】 期間 : 2021年10月1日(水)~ 合格者が最小開講人数の15名程度に達するまで 選考結果: ご応募受付後、適宜ご連絡予定 【開講日程検討期間】 期間 :仮応募受付期間終了から1週間程度で、開講日程を決定いたします。 開講時期:仮応募受付終了から概ね2ヶ月~3ヶ月後を想定しています。 【本応募受付期間】 期間 : 開講日程決定 ~ 2ヶ月程度 選考結果: ご応募受付後、随時ご連絡予定 |
|---|---|
| 受講料お支払い時期 | 本応募受付開始後。詳細は合格者に別途ご連絡します。 |
| e-ラーニング | 週1回の講義配信を15回程度で構成予定。 eラーニング配信期間は4ヶ月〜6ヶ月程度を予定 |
| オンラインゼミナール | 月に1回程度、ZOOM等のオンライン会議ツールを利用したゼミナールを実施。日程につきましては、参加者のみなさんのご都合を考慮して決定します。 |
| 開講式集中研修 | 日程につきましては、開講後、参加者のみなさんのご都合を考慮して決定します。 所要時間:半日程度で実施 会場:オンラインでの開催を予定 |
| 修了式集中研修 | 日程につきましては、開講後、参加者のみなさんのご都合を考慮して決定します。 所要時間:2日間で実施 ※新型コロナウイルス感染症の状況により、現地集合型か、オンライン型か、実施方法は後日決定 (現地集合型の場合) 開催場所は未定。開講後、ご案内いたします (オンライン型の場合) ZOOM等のオンライン会議ツールにて実施予定 |
e ラーニングについて
毎週60-80分程度の動画を配信します。1講義につき、レクチャー映像の視聴、⼩テスト、レポートで構成されます。また、 指定図書・⽂書を読みレポートを提出していただきます。
e ラーニングを使⽤する事で、説明を聞きながら資料を⾒返したり、⾃分のやり⽅で理解を深めることが可能です。
コミュニティに所属して、チームでステータスを共有をすることも出来ます。

e ラーニングについて / 学習の流れ
- レクチャー映像
- 小テスト
- 他受講⽣の感想へ
コメント(2 点)
- レクチャー映像
- 小テスト
- 他受講⽣の感想へ
コメント(2 点)
- レクチャー映像
- 小テスト
- 他受講⽣の感想へ
コメント(2 点)
- レクチャー映像
- 小テスト
- 他受講⽣の感想へ
コメント(2 点)
e ラーニングについて / カリキュラム(予定)
| 0 | 開講挨拶とオリエンテーション | 本講座の成果を最大化するためには何が重要なのか。本課程を修了した第1期生の体験に基づくレクチャー等も踏まえて、各自の自律的な学習計画策定の指針をまとめていく。 |
|---|---|---|
| 1 | 【マネジメント01】都市経営課題の発見・解決のための情報・知識インフラ | 都市経営の課題を発見し解決するための情報・知識インフラとして、「図書館」をどう位置づけるか。図書館が目的でありえた時代はすでに終わりを告げており、新たな図書館のデザインが求められている。この出発点を明らかにする。 |
| 2 | 【マネジメント02】ケーススタディ1:オガールプロジェクトと紫波町図書館 | オガールプロジェクトと紫波町図書館の事例に基づき、図書館が閉じずに地域と密接に結びつきあうための取り組みや公民連携を支える図書館の基礎力を理解する。 |
| 3 | 【マネジメント03】ケーススタディ2:須賀川市民交流センターtette〈前編〉 | 須賀川市民交流センターtetteのプロセスを記録した映像「須賀川市民交流センターtette 開館までの記録」を観て、多様な協働による施設整備のプロセスを学ぶ。 |
| 4 | 【マネジメント04】地域社会、地域経済を支援する図書館 | 『市民の図書館』からはじまった市民に開けた図書館の歩みを学び、近年の図書館整備においてテーマになる「図書館が地域社会、地域経済を支援する」ということを事例に基づき考える。 |
| 5 | 【パートナーシップ01】TSUTAYA図書館、再考 | TSUTAYA図書館の問題を、「公共性」「地域経済」「デザイン」の3つの観点から検証し、現代の図書館における「公民連携」の可能性と課題を考える。 |
| 6 | 【パートナーシップ02】ケーススタディ3:須賀川市民交流センターtette〈後編〉 | 須賀川市民交流センターtetteも事例に基づき、「複合を超える融合」施設の核となる図書館の整備と運営の実践について学び、公共施設における融合の可能性を創造する。 |
| 7 | 【パートナーシップ03】ケーススタディ4:新智頭図書館「ちえの森ちづ図書館」と「ちづみち構想」 | 新智頭図書館「ちえの森ちづ図書館」と「ちづみち構想」の事例に基づき、図書館とまち育て事業の連携について学び、図書館を基点としたまちなか整備のあり方を考える。 |
| 8 | 【パートナーシップ04】民間公共の系譜〜近代の私設図書館から現代のカフェまで〜 | 近代、日本各地に勃興した民間資本を核とした公共性を持つ図書館事業の系譜から、2000年代、都市における小さな公共性を持つカフェなどのコマーシャル空間の展開まで、近代から現代を辿り、より多様な「公民連携」のあり方を考える。 |
| 9 | 中間発表 | プロジェクト型課題についての各自の検討状況をプレゼンテーションしあい、相互にレビューして、ブラッシュアップする。 |
| 10 | 【トピック01】子育て支援 | 社会課題としての「少子化」を受けて、行政による子育て支援のあり方と図書館の接点を探る。人を育てる施設としての図書館の可能性を考える。 |
| 11 | 【デザイン01】知識とは?情報とは?現代における知識情報環境を考える | インターネット以降の知識情報環境及びメディアの変化を学ぶ。人工知能×AR/VRによる「知る、わかる」という体験の変化と都市への影響を考える。 |
| 12 | 【デザイン02】ケーススタディ5:県立長野図書館「信州・学び創造ラボ」 | 県立長野図書館「信州・学び創造ラボ」の事例に基づき、公共図書館のリノベーション(部分改修)における、計画・設計・運営・利用がシームレスにつながったデザインプロセスを学び、コモンズの可能性を考える。 |
| 13 | 【デザイン03】ケーススタディ6:各地に展開するスモールライブラリー | まちじゅう図書館、まちライブラリー、情報ステーション、ルチャ・リブロ、泊まれる図書館暁、他の事例に基づき、私設図書館やネットワーク図書館の課題と可能性を考える。 |
| 14 | 【デザイン04】2030年、図書館は視えなくなるか⁉ | AI時代の知識情報環境を想像し、物理的な場所、紙の本を持たない視えない<図書環>(図書+環境)の可能性を創造する。 |
| 15 | 【トピック02】図書館DX町の図書館整備の実践 | 現在進行中のプロジェクト事例を生の素材として、地域の小規模自治体における図書館整備について、その課題と可能性を探る。 |
| 16 | 集合研修及び修了式 | 都市経営的な観点から公共性を持つスモールライブラリーのアイデアを具体的に考え、プロトタイプとなるプロジェクトについて発表及び講師からの講評を行います。 |
- 本講座の新規コンテンツは、⽕曜⽇を基本として配信されます。
- eラーニングコンテンツは受講期間中のみ、何度でもご覧いただけます。
- お盆、年末年始時に配信をお休みさせていただく場合がございます。その際は、事前にご連絡いたします。
- 本スクールでは他者視点も共有することで洞察を深めることを意図し、「映像視聴」または「自身のレポート提出」+「他受講⽣の感想またはレポートへのコメント(計2回)」を⾏うことで、各回の学習が対応完了となります。
- e ラーニングを受講いただくためのパソコン等の機材や環境の準備、課題図書の準備、ならびに集合研修参加に関わる宿泊先・⾷事・移動交通・個別の必要備品(ノートパソコンまたはタブレット端末等)に関わる費⽤はご⾃⾝にて対応をお願いいたします。本受 講料には含まれません。
- 本講座の配信映像数ならびに課題図書の点数が変更になる場合があります。
- お申し込み者数が最小催行人数に達しなかった場合には、開講を⾒送る場合があります。予めご了承ください。
事前対応のお願い
本スクールでは、e ラーニング受講に際し、プロフェッショナルスクール株式会社が提供する 「AirLec(エアレック)」を活⽤いたします。お申し込みに際して、同システムを利⽤できることが前提となり ますので、各⾃で動作確認をお願いいたします。なお、動作確認に際しては、AirLec へのユーザー登録が必要 となります。
最新バージョンのGoogle Chromeをご利用ください。
横表⽰でお使い下さい。
最新バージョンのOS での利⽤をお勧めいたします。
iOS、Android は、最新のiOS でのご利⽤をお勧めします。
Android は機種により動作が異なるため、個別の表⽰異常等が発⽣する場合があります。
- ※ 無線LAN をご利⽤の場合、途中で接続が切れる可能性があります。
- ※ 上記環境を満たしていても、個々の環境により授業コンテンツの再⽣がうまく⾏かない場合もありますので、 予めご了承下さい。
集合研修について
eラーニングで修得した知識を、実践に結びつけるため、受講期間中に開講と修了時に集中研修を2度実施いたします。集中研修では主に個別にチームを組んで⾏う「演習」と、 コーチによる「レクチャー」から成り、次世代図書館に向けた具体的な事業計画や行動計画を策定していきます。

エグゼクティブ・コーチ

- 岡本真
アカデミック・リソース・ガイド株式会社(arg) 代表取締役
1973年生まれ。1997年、国際基督教大学(ICU)卒業。編集者等を経て、1999年、ヤフー株式会社に入社。Yahoo!知恵袋等の企画・設計を担当。2009年に同社を退職し、1998年に創刊したメールマガジンACADEMIC RESOURCE GUIDE(ARG)(週刊/4000部)を母体に、アカデミック・リソース・ガイド株式会社(arg)を設立。「学問を生かす社会へ」をビジョンに掲げ、各方面での情報・知識・サービスの創出事業や産官学民連携事業を展開。著書(共著含む)に『未来の図書館、はじめます』(青弓社、2018年)、『未来の図書館、はじめませんか?』(青弓社、2014年)、『図書館100連発』(青弓社、2017年)、『これからホームページをつくる研究者のために』(築地書館、2006年)、『ウェブでの<伝わる>文章の書き方』(講談社現代新書、2012年)、『ブックビジネス2.0』(実業之日本社、2010年)ほか。

- 李明喜
デザイナー。アカデミック・リソース・ガイド株式会社(arg)取締役 CDO。1966年生まれ。1998年、デザインチームmattを立ち上げ、商業&公共施設、アートスペースの空間デザインやキュレーション業務を行う。2014年より、arg社のデザイナーとして、須賀川市、板橋区、西ノ島町、智頭町などで、図書館を中心とした新しい文化施設づくりや地域のデザインにあたっている。図書館管理運営計画、ミュージアムキュレーションなどを担当した「須賀川市民交流センターtette」は、2019年グッドデザイン金賞を授賞。
図書館専門雑誌LRGでは、「図書館のデザイン、公共のデザイン(第20号)」、「マンガという体験、図書館という環境(第24号)」、「情報学は哲学の最前線(第27号)」の責任編集を担当した。

- ⽊下⻫
⼀般社団法⼈エリア・イノベーション・アライアンス代表理事∕⼀般社団法⼈公⺠連携事業機構理事∕内閣府地域活性化伝道師
1982年東京生まれ。早稲田大学高等学院在学中の2000年に全国商店街合同出資会社の社長就任。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、一橋大学大学院商学研究科修士(経営学)修了。08年、熊本城東マネジメント株式会社設立、並びに09年一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンスを設立。全国各地の事業型まちづくり会社に出資、経営参画する傍ら、都市経営プロフェッショナル・スクールを開校し、既に300人以上の受講生が卒業、現在50都市以上の事業支援を行う。
主著に「地元がヤバい…と思ったら読む凡人のための地域再生入門」(ダイヤモンド社)、「福岡市が地方最強の都市になった理由」(PHP研究所)、「地方創生大全」(東洋経済新報社)、「稼ぐまちが地方を変える」(NHK新書)、「まちで闘う方法論」(学芸出版)、「まちづくりの経営力養成講座」(学陽書房)など。
コーチ

- 岡崎正信
一般社団法人公民連携事業機構理事、CRA合同会社代表社員
株式会社故郷の山専務取締役他に、オガール紫波(株)取締役事業部長、岡崎建設(株)事業部長。1995年に地域振興整備公団(現都市再生機構)に入団し、2002年に退団するまでの間、東京本 部、建設省都市局都市政策課、北海道支部などで地域再生業務に従事。現在は家業と共に、岩手県紫波町が出資する「オガール紫波株式会社」の事業部長として、紫波町の公民連携事業を企画推進、現在は株式会社オガールプラザ代表取締役として中核施設を経営している。内閣府地域活性化伝道師。

- 礒井純充
まちライブラリー提唱者、森記念財団普及啓発部長、大阪府立大学客員研究員。
経済学博士。まちづくり、場づくり、まちライブラリーを柱に研究中。森ビルで「六本木アカデミーヒルズ」をはじめ文化活動に従事。11年より「まちライブラリー」を提唱、全国約750カ所以上で展開。13年まちライブラリー@大阪府立大学で「蔵書ゼロ冊からの図書館」、「マイクロ・ライブラリーサミット」を実施、15年には大阪市の商業施設もりのみやキューズモールBASEにまちライブラリーを開設し、4年間で60万人以上来館するまでに育てる。19年には南町田グランベリーパーク、東大阪文化創造館にも誕生。グッドデザイン賞受賞。著書に『本で人をつなぐ まちライブラリーのつくりかた』(学芸出版)他。

- 鎌田千市
1970年生まれ。紫波町企画総務部 企画課長。
大学にはスポーツ推薦で進み、学生時代は体育館と仙台国分町を行き来。農家の長男ということもあって、地元の役場職員に。総務、税務、商工観光と勤め、田舎町で平穏な14年間を過ごす。
転機は2007年の春。「断ることは想定していないから。岡崎さんがいるから大丈夫。」と言われ、東洋大学大学院公民連携専攻への教育派遣を命じられる。それから13年、オガールプロジェクト(紫波中央駅前都市整備事業)をライフワークとして、オガール・デザイン会議は建築やランドスケープ、デザインの専門家で構成され、金融、エコ、工務店、不動産、NPO、地域づくりといった分野の方々とつながり、刺激を受け続ける。公民連携によるまちづくり「まち 人 オガール」に関わり、汗をかきながらも、楽しくてしょうがない!という毎日を過ごしている。

- 高橋堅
紫波町企画総務部長
昭和58年紫波町役場入庁。紫波町初の公共下水道建設で主に機械設備整備及び施設維持に従事。その後、人事、市民協働、企画調整、財政の担当。この間に岩手県内の県職員、市町村職員の有志で構成する自主研究グループに立ち上げメンバーとして参加し、自治体の制度や政策法務などを学ぶ。平成19年からオガールプロジェクトの担当室長となり、現在に至る。

- 三浦丈典
1974年東京都生まれ。早稲田大学、ロンドン大学ディプロマコース修了、早稲田大学大学院博士課程満期修了。2001年〜2006年までNASCA勤務。2007年設計事務所スターパイロッツ設立。大小さまざまな建築やまちづくりに関わりつつ、自らシェアオフィスや撮影スタジオも運営する。最近では各地でまちづくりやエリアリノベーションに則した図書館の企画・設計にも携わる。「道の駅FARMUS木島平」で2015年グッドデザイン金賞を受賞。著書に「起こらなかった世界についての物語」、「こっそりごっそりまちをかえよう。」、『いまはまだない仕事にやがてつく君たちへ』など。

- 手塚美希
紫波町図書館主任司書(紫波町企画総務部情報交流館)
1975年秋田県生まれ。浦安市立図書館に専門非常勤職員として5年、秋田市立中央図書館明徳館に臨時職員、秋田県立図書館に非常勤職員として7年勤務。2010年紫波町企画課公民連携室に図書館専門嘱託員として採用され、紫波町図書館立ち上げを単身赴任しながら行う。2012年8月開館、ライブラリー・オブ・ザ・イヤー2016優秀賞受賞。2019年6月、アメリカ図書館協会(ALA)年次総会2019でジャパンセッションに参加。現在も紫波町図書館の司書として勤務しながら、愛知との往復生活を送っている。好きなものはみんなで飲む日本酒。

- 嶋田学
奈良大学卒。1987年大阪府豊中市立図書館、1998年滋賀県旧永源寺町図書館準備室、2005年から東近江市立図書館での勤務の傍ら2008年同志社大学大学院総合政策科学研究科を修了(政策科学修士)。2009年同大学政策学部嘱託コーチの兼業などを経て、2011年瀬戸内市の新図書館開設準備室長。2016年から瀬戸内市民図書館館長。2019年から奈良大学文学部文化財学科教授(司書課程担当)。2021年から京都橘大学文学部歴史遺産学科教授。著書に『図書館・まち育て・デモクラシー -瀬戸内市民図書館で考えたこと-』(青弓社)、『図書館サービス概論』(共著、ミネルヴァ書房、2018年)など。

- 平賀研也
県立長野図書館 前館長、たきびや
1959年仙台生まれ、東京育ち。法務・経営企画マネージャーとして企業に勤務。その間、米国中西部にくらし、経営学を学ぶ(イリノイ大学経営学修士)。2002年長野県伊那市に移住。公共政策シンクタンク(総合研究開発機構)の研究広報誌編集主幹を経て、07年4月~15年3月公募により伊那市立伊那図書館館長。15年4月より県立長野図書館館長(〜2020年3月)。実感のある知の獲得と世界の再発見に寄り添い、情報と情報、情報と人、人と人をつなぎ多様なコミュニティを育む共知・共創の新たな公共圏の構築を目指す。
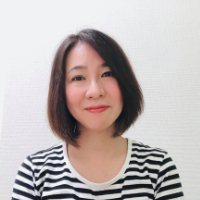
- 萬谷ひとみ
新宿区立中央図書館副館長(管理係長)
1990年特別区職員として板橋区立清水図書館に配属される。その後、国民健康保険課、板橋第五中学校を経て、1999年区間交流で新宿区へ異動し、新宿区立四谷図書館、中央図書館に勤務。その後、新宿歴史博物館、介護保険課、情報システム課を経て、2009年中央図書館へ異動。2011年係長級職員、2013年エキスパート職員として、中央図書館の移転や下落合図書館図書館の開設などに従事し、現在に至る。都市経営プロフェッショナルスクール・次世代図書館専門課程1期生。
申込特典について
⾼く、熱意と⾏動⼒に溢れる卒業⽣ら連携し、各地で同時多発的に公⺠連携事業を実現させていくためにも、
以下の「申込特典」を設け、募集を実施いたします。特典は併⽤も可能です。
 55,000 円
55,000 円本スクールでは強い意志を持って受講される個人の⽅を応援しています。そのため、組織派遣としてではなく⾃⼰負担にて受講される個⼈の⽅へ、本特典を適⽤いたします。
- 他割引との併⽤が可能です。
- 特典利⽤者は申込フォームの所定欄にチェックを⼊れてください。
- 本特典利⽤に際して、法⼈・団体名での領収書および請求書の発⾏は⾏いませんので予めご了承ください。
 55,000 円
55,000 円本スクールでは本スクールの他課程の修了生の方のさらなる学びを応援しています。そのため、都市経営プロフェッショナルスクールの過年度他課程の修了者を対象として、本特典を適用いたします。
- 個人受講応援割引との併⽤が可能です。推薦割引との併用はできません。
 55,000 円
55,000 円本スクールでは受講者のネットワークを重視しております。そのため、本スクール各課程の受講経験者から推薦を受けた方を対象に、本特典を適用いたします。
- 個人受講応援割引との併⽤が可能です。修了生割引との併用はできません。
- コーチ・関係者からの推薦による特典はございません。
- 特典利⽤者は申込フォームにて必要事項をご記⼊ください。
